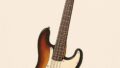巷では「手打ち=悪」の様な言われ方をしていますが、人それぞれ結果が出やすいスイングってものがあります。
無理に体だけで打ちに行って「どスライス天国」になるより、手打ちでビシッと当てた方が結果が出る場合もありますし、青木 功プロなどは手打ちだと公言しているくらいです。
特に何がなんでも100切りを達成したい!という人は、手打ちでラウンドした方が結果に繋がる可能性もあります。
手打ち反対派の人達も、自分では体で打っている気がしているだけで、傍から見るとかなり手を使っているケースも多々ありますので。
手打ちのイメージが強いスイングではありますが
始めに書いた通り、近年ボディーターンスイングが善で、手打ちスイングは悪と言われがちではありますが、個人個人がどちらのスイングに向いているか?だけの事でもあります。
インパクト時の再現性、ここさえしっかりとしていれば自ずと結果に繋がってきます。
腕をできるだけ固定して体を回してインパクトした方が再現性が高くなる人もいますし、反対に手を使ってインパクトした方が安定する人もいます。
体幹の強さ、筋力、身長の全てが個々においてバラバラなので、決して全員が同じスイングにはなりません。
やや日本のスポーツの傾向として、良い型を身に付ければ、良いボールが打てるという事に囚われる面がありますので、野球にしても海外の選手の様なクセのあるフォームでプレーする人が少ないですね。
子供の頃から半強制的にフォームを練習させられて固められるからです。
良いボールを打つには、良いインパクトが必要不可欠で、その良いインパクトまでのプロセスが個々において若干の違いがあるのは当然です。
そんな訳で、半分手打ちの要素が入っていますが、左一軸での水平スイングを紹介します。
ハマる人にとっては最も簡単な方法になるのでお薦めのスイングの一つです。
実は筆者も割と好きなスイングとなります。
好奇心旺盛な事、またこのブログのネタとして色んな理論を試してみてはいますが、時折スイングがミックスになってしまい、おかしくなった時などにこれに戻って修正したりしています。
左手は強めのフックグリップで握ります。
あまりフェースを開閉させない為に、左手は強めのフック(ストロング)グリップで握ります。
それも「こんなに??」ってなくらいのストロンググリップです。
極端な話し、真上から乗せる様にグリップして左手の甲とクラブのフェースが直角になるくらいのイメージです。
それによって左手の甲を上に向けたまま横に水平に振れば、理屈上ではフェース面が変わらずに移動する事になります。
実際には遠心力とクラブ重量でフェースが開く方向に動くことになりますが…。
これについての対策は後で説明します。
またインパクト付近でのクラブフェースが通る軌道ですが、ボールを挟んで「前後20㎝」くらいはパッティングの様に限りなく真っ直ぐに移動させます。
この部分のイメージ作りの為にやや手打ちになるとも言えます。
このボールを挟んだ前後20㎝(合計40㎝)くらいを平行移動させる事によって打ち出しはストレートからややフェードになります。
テイクバックからトップ、トップから切り返しまでの動き
テイクバックからトップまでですが、まず最初にボールから後ろ20~30㎝くらいをヘッドを平行に移動させてスタートし、そのまま低く引いたヘッドが止まって左手にコックが入ってトップに向かって上がっていく訳ですが、低いままで直線的に移動してきた腕がそのまま正面を向いたままの胸に当たって止まり、そこから強めのフックグリップで握っている左手親指方向へコックが入り、勢いでフェースがクルッと少し返って空を向く感じになりトップが完成します。
そこからの切り返しは、空を向いたフェースのままヒールから左手小指の方向にチョップをするように振り出していき、そこからボールを中心にした40㎝~50㎝くらいを平行移動でパターで払う様にしてインパクト、そのままトゥが飛球線方向に向くように返してフィニッシュという流れです。
ボールの前後20~30㎝の直線の動きを自分で作る事から、やや手打ちの様な意識になります。
割と手先や感覚が器用な人で、この方が再現性の高いインパクトが可能な方にとっては、かなり安定感のあるスイングになります。
実際のスイングは前傾しているというだけで、もしも直立していたら体(胸や肩)の回りを水平の振っているだけのイメージなので軌道を目で確認できますし、インパクト部分も自分で作れるので合う人にとっては最高のスイングになる可能性を秘めています。
ボディーターンスイングを一生懸命に練習してもいまいちスコアに繋がらないという方は、一度試してみてほしいと思います。
意外にも目から鱗になるかもしれません。
実はこれはワタクシが、少しお金を払って習ったオーストラリア系の理論なのです。