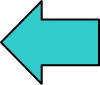
まずは練習場と現場での違いを理解する。
練習場にて完璧だ!と思って、いざラウンドに意気揚々と出陣したものの、思ったほどに結果に繋がらなくてガッカリするという経験は無いでしょうか?
逆に練習場で思う様に当たらずに、恐る恐るラウンドに行ってみたところ、思いの外しっかりと打てて安心したという経験もあると思います。
これに関しては「芝」と「マット」の差だったりします。
地面の素材の違いにプラスして、練習場のレンジボールと本球の違いも出てきます。
練習場のレンジボールは耐久性を重視されていて、また練習場の立地条件によっては、ネットから飛び出さない様にできるだけ飛ばないボールを用意されているケースもあります。
ボール自体、同じダンロップの練習球でも印字されている文字の色で飛距離が違ってくる様に設計されています。
耐久性を上げて、飛距離を抑えるという事は表面の素材を厚くして長持ちする物にした上に反発力を下げる様になっているので、本球に比べてフェースに乗りやすくスピンも入りやすくなります。
つまりアプローチなどに関しては上手くなった錯覚もしますし、ドライバーなどではスピンが増える事でややフェードになりやすい傾向があります。
それを知らずに、
「あれ?今日はドライバーが擦り球になるな?」
などと考えながら、ラウンド前日にレンジボールでストレートやドローになる様に調整すると、翌日の1ホール目からチーピンなどが出て、いきなりのOBスタートになったりする危険性もあります。
今は大分改善されたとは思いますが、昔の国産アイアンなどは練習場マットでナイスショットが出やすい様にバウンス角を少なめにしてある物が多かった様です。
バウンス角が大きいと、マット上では最初にバウンスが当たる事で軽くダフッた感触になるからです。
PINGのクラブなどはバウンス角がかなり大きめに設定されているので、マットで練習する際には一番低いティーを挿して練習するのがお薦めです。
スイング理論も同様に、練習場と現場の違いを理解する。
ほぼ平坦なマット上で何度も打てる練習場の環境では、あらゆるスイング理論を試す事ができますし、比較的うまく当てる事も可能です。
しかし、身体を大きく使ったスイングは傾斜などではバランスをキープする事が難しく、そこまで体幹を鍛えている訳ではないアマチュアにとって、傾斜地で体重移動をしながら軸をキープするのは至難の業です。
自分も散々試した結果、結局スコアがまとまるのは左一軸スイングだと確信しています。
ドライバーからアプローチまでほぼ同じスイングで打てるのも魅力です。
クラブによって打ち方を変えるのは、毎回ワンチャンスしかないゴルフというスポーツにおいてリスクが高くなるだけです。
おすすめの左一軸の打ち方。
まず、70%以上左に乗った状態でアドレスを取ります。
まあ、アプローチの時の様なアドレスです。
準備として左のつま先は少し(30°くらい)開いておきます。
そのまま左肘は軽く左脇に触れているくらいの感じで、左膝を折って左足のつま先に体重を乗せます。
すると自然に骨盤が回転して、右膝は自然に伸ばされ、クラブヘッドは遠心力で後方に動き始めます。
骨盤が回りきって止まると、後方に回り始めたクラブヘッドに急ブレーキが掛かって自然にコックが入ります。
これでトップが完了します。
次に切り返しになりますが、左膝を伸ばして勢いをつける事も可能ですが、慣れないうちはタイミングが難しくなりますので、テイクバックで折れたコックをほどいてクラブヘッドがグリップを持っている手の真下に戻るイメージでそのままボールにアタックします。
それだけでもクラブヘッドの勢いに引っ張られる様に腰と体は自然に左に回転します。
慣れてきたら左膝を思いっきり伸ばす事で骨盤の回転の勢いが増し、飛距離が見込める様になります。
その際に注意するのが、インパクトまでは絶対に右手は左手よりも下にある意識でクラブヘッドをリリースする事です。
イメージ的に腕とクラブが右回りにひっくり返っていて、フェースもボールじゃなくてとんでもない方向を向いている気がして気持ちが悪いですが、これに関してはゴルフのスイングはこういう風に道具を使うものだと割り切って慣れるしかありません。
ここの形に関しては、どのスイング理論においても共通で絶対に必要になる形です。
ボールにフェースを向ける動きは左回りで上から叩く動きになってしまうので、できるだけ早く腕もクラブも右に回した方が安定して当たるという事を体に沁み込ませてください。
それさえできれば、後はクラブヘッドを手の下に落とすだけで打てる様になりますので。

