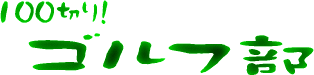いきなりリーディングエッジで上から打つ意識では、バウンスは使えない。
「ダウンブロー」
ゴルフ、特にアイアンショットでは必ずと言って登場するワードですが、解釈次第でどうにでもなる悩ましいワードでもあります。
「上から打ち込む」とも言われますが、それはどういった状態を指すのかすら、思いの外しっかりと語られている事が少ないです。
と言うより、この感覚は各々が持っているイメージなので、本当の正解というのは誰にも分からないのかもしれません。
大抵、上から打ち込むと言われれば、右側後方に振り上げたクラブを飛球線方向の左側前方に振りながら、刃(リーディングエッジ)や、フェース面でボールを潰すように打ち込むのが「ダウンブロー」だとイメージするかと思われます。
つまり、右に振り上げたクラブのリーディングエッジ、つまり刃の部分でボールに対して上から打ち込んでいくイメージですね。
しかし、その理屈であれば、ゴルフクラブはリーディングエッジ(刃)の部分さえあれば良いという事になります。
それでは、クラブメーカーがソールの厚さや形状、バウンス角などを一生懸命に大きくして、できる限り簡単になる様に設計しているのは何故?という事にもなりますよね。
そもそもボールの直径以上にクラブヘッドが上に上がっていれば、そこからボールを打つには必ずダウン軌道、つまりダウンブローになる訳です。
そこで、ワタクシが思うダウンブローについて書いていきます。
バウンスを使って打つ意識で左に振り抜く(スイングレフト)
バウンス角とはクラブのソールに付いている角度です。
これが芝からの抜けを良くするのに一役買っています。
フェースから見て後ろ側についているものなので、どうやって使うの?ダフった時専用のお助け機能?
という気もしてしまいますが、常にここを使って打つ事でヘッドの抜けが安定します。
「スイングレフト」
クラブ、正確にはグリップエンドを左に引き抜く様に振ってボールにインパクトし、インパクトと同時にヒールから「バターをバターナイフで薄く削る様に」バウンスを滑らせながら振り抜きます。
この時、削る方向は飛球線側ではなく、自分の左サイドへのイメージになります。
この形でヒールからボールを切る様にインパクトしてその後にヘッドを前に出していく様に振り切ると、バウンスが出て芝の上を滑りながら遠心力でロフトが立ちながらインパクト、そのインパクトの衝撃でヘッドが下がり、リーディングエッジが芝に当たる事でターフが取れます。
そこまでは、ずっと右手は左手の下にある状態のままで、遠心力とシャフトを前方にローリングする動きでロフトが立ってくるイメージです。
反対に、最初から左回転でリーディングエッジ部分を上から打ち込むイメージでは、一見同じダウンブローに見えますが、ボールにインパクトした直後にリーディングエッジとヘッドのトゥ部分が芝に突き刺さる事で、短くて深いターフが取れるのが特徴です。
バウンスを使って左に振ったダウンブローでは、ボールにインパクトした衝撃で、ヘッドがロフト角とシャフトの傾斜角の分だけボールの下に潜り込みながら、カンナで削った様な薄くて長いターフになります。
ウェッジや短い番手の方が、45度前後のロフト角のヘッドと、短いシャフトの小さい半径によって鋭角に入る為、より深くて大きなターフが取れるという事になり、長い番手は20度台のロフト角で、シャフトも長くなる事から入射角度が緩やかになるのでターフはあまり取れなくなります。
つまり「素振り」をしただけで多量のターフが取れているのであれば、それはリーディングエッジとクラブのトゥを、上から手を返して打ち込んでいるスイングであって、このスイング自体が間違いとは言いませんが、現代のPGAの選手達のようにできるだけ手を返さないでゾーンで振っていくスイングとは別理論の打ち方だと言えます。
本来であれば、ボールへのインパクトの衝撃が無ければヘッドは必要以上に下に潜らないので、素振りであれば芝の上をバウンスで擦る感じになり、バスンバスンというバウンスが当たる音と共に、表面の芝が少しだけ削れて舞い上がる感じになります。
このスイングレフトでバウンスを使ったインパクトを目指してスイングすると
バウンスを意識してスイングができると、副産物としてスイングそのものが良くなったりもします。
体を開いて打てる様になる。
昔ながらの日本式(決してこれがダメという訳ではありません)のゴルフでスイングを作った方に多い、特に右手が左手の上を通る様に「手首を返して打つ」タイプの方には理解ができないのが「体を開いて打つ」という動きです。
実際にシングルハンディの方でも手を返して打つスイングでゴルフを作った人は「体を開くってのが分からないんだよな。」と言います。
もう長年の経験で、右手を返しながらインパクトするタイミングなどを完璧に習得し、結果シングルまでなっていますので、スタイルとして完全に確立されているのでしょう。
確かに、この「右手を返す」スイングと「体を開く」は水と油、究極に相性が悪いのです。
手を返して打つスイングの場合は、体は開かずにむしろ後ろを向いたままくらいの状態で振る事でちょうど真っ直ぐのボールが出やすくなります。
反対に「手を返さず」にインパクトまで持ってくるには、右腕と右手が下のまま体を開いてグリップエンドを左サイドに引き込こみながらヘッドを出さなければ、ボールの位置までヘッドを持ってくる事自体が不可能になります。
手を返さずに打つスイングにおいては、体を止めたままでは手首をほどいてヘッドをリリースする以外、どうやってもヘッドをボールの位置まで届かせる事ができません。
勝手に頭が残ります。
「頭を残す」というワードも散々聞いたと思います。
しかし、無理やり頭を元の位置に残そうとしても首を痛めるだけです。
さらにその結果、手を返しながら頭と胸を後ろに残す…というインパクトの形になります。
この「頭を残す」に関しても、必要分なだけ勝手に残るが正解です。
手首を返さずにインパクトの形まで持ってくる為には、軸がほんの少しだけ後ろに残っているくらいでなければ、グリップエンドを左サイドに振っていく事は不可能です。
左回りで頭を左に突っ込んで上から打ちに行けば、左サイドにグリップを振り抜くスペースが無くなり、同時にヘッドが抜けていく道も無くなります。
反対に頭を残し過ぎれば、ヘッドをボールに届かせようと手首がほどけてクラブヘッドが放り出される様なインパクトになります。
(ドライバーでは若干この感覚になりますが。)
なので、結論として、
「右股関節前にグリップエンドを自然落下させた瞬間に、同時にグリップを左に引き込む様に鋭く回転してインパクト」
ここを目指せば、勝手に体が必要な分だけ開いたり、必要な分だけ頭が残ったりするのです。
自分でする事は、コア(体幹)を中心にコンパクトに鋭く回る意識だけですから。
「頭を残せ!」
どれくらい残すの?
「アドレスの位置から1㎝も動かさない意識で!」
首を捻挫するわ!!
「明治の大砲になってる!」
頭を残せって言うから、しっかり後ろに残したのに!!
という事が、巷ではまことしやかに言われているのです。
目指すポジション(グリップを左に引き込むなど)を明確にしないまま、途中の形だけを切り取った話しをされても混乱するだけですね。
最初は少し難解ですが、このグリップエンドを左に引き込んむスイングが理解できると、ショットはすこぶる安定しますし、ドライバーなどはコツが分かるとシャフトがよりしなって今まで以上に飛ぶ様になります。
フィギアスケートのトリプルアクセルの様に、体幹を使ってコンパクトに回転するのが一番速くてパワーが出ますから。
またグリーン周りからのアプローチショットも、体の返しでボールを下投げする様に運ぶ感覚になり、ビタビタ寄る様になります。
そして何よりもバウンスが滑る事で、しっかりとダウンブローで打ち込んでもダフらずに抜け、その移動距離からなる摩擦抵抗によりしっかりとしたスピンが入ります。
「パンッ!!」というバウンスが芝を叩く音と共にヘッドが抜けて、キュキュッっと止まるショットを目指して下さい!
バウンス角の大きいPINGのアイアン PINGのアイアンは昔からバウンス角が大きく、芝の上から打った時の抜けが絶妙で、アイアンが上手くなった錯覚が起きるほどです!
PINGのアイアンは昔からバウンス角が大きく、芝の上から打った時の抜けが絶妙で、アイアンが上手くなった錯覚が起きるほどです!